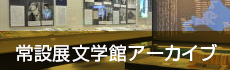道内で個人、団体が発行されている文芸誌を紹介します。
文芸誌紹介
逍遙通信
『逍遥通信』について
澤田 展人
2016年8月5日、創刊。澤田展人が編集・発行する個人文芸誌である。誌名には、気ままな散歩をしているときに頭に浮かんだことを便りとして知人に送る、といった意味を込めた。創刊号には、久間十義と外岡秀俊のエッセイ、澤田展人の小説を掲載した。
現代に生きることの痛み、苦しみと格闘する作品を載せ、読者とともに考えたい、という意図から自由な寄稿を呼びかけている。徐々に寄稿者が増え、近刊の第9号は寄稿者30名、ページ数がおよそ460ページとなっている。第2号、第3号発刊時には、支笏湖畔に居を構える鹿田幸年宅に執筆者が集まり、徹夜の合評会を行った。新型コロナ感染が広がってから合評会を中止していたが、現在、復活の道を探っている。
同人制をとらず、読者に任意のカンパを呼びかけることで制作・発送の費用を賄っている。読者の輪が広がり、現在、カンパを財源とする発行が実現できている。
創刊号から欠かさず作品を寄稿していた外岡秀俊が2021年急逝し、翌2022年に『逍遥通信第7号 追悼外岡秀俊』を発行した。外岡の仕事に注目していた全国の人から入手の希望があり、読者が増えた。外岡が本誌に執筆した作品は遺稿集『借りた時間、借りた場所』(藤田印刷エクセレントブックス)として単行本化された。
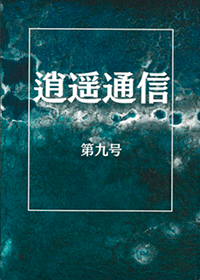
「逍遙通信」
第9号 2024年5月
寄稿作品数に応じて柔軟にページ数を増やしているので長篇作品を掲載することが可能になっている。先日逝去した友田多喜雄の自伝的な長篇連作詩「幼い日々」、北村巌による小林多喜二・島崎藤村・新宿中村屋をめぐる評伝的作品、澤田展人の長篇小説など長尺作品がこれまでに掲載された。
分断と敵対、貧困と差別が進行する世界に文章表現によって抗い、よりよき生のあり方を希求する作品を掲載することを本誌発行の意義と考え、今後とも広く寄稿を呼びかけていきたい。
(「逍遥通信」編集発行人)
詩誌「フラジャイル」~詩誌「青芽」後継~
詩誌「フラジャイル」
~詩誌「青芽」後継~
柴田 望
小熊秀雄の詩友小池栄寿に師事した富田正一が復員後「これからは心の時代だ」と決意し、1946年に詩誌「青芽」を創刊、以降72年間発行を続けた。「青芽」後継誌として2017年12月に詩誌「フラジャイル」創刊。旭川の詩文化を大切に次の世代へ運ぶ「こわれもの」の荷札。富田正一の想いを引き継ぎ、「しがらみのない自由な創作の場」を築くことを目標に、創刊メンバーは柴田望、木暮純、二宮清隆、山内真名。2号から6号までと14号に吉増剛造氏の北海道講演を収録。2024年に20号発行までの7年の歩みで、同人参加は小篠真琴、荻野久子、冬木美智子、菅原未榮、星まゆみ、中筋智絵、鷲谷みどりなど道内のみならず、金井裕美子、福田知子、佐波ルイなど全国に広がる。年3回発行。20号(記念号)はゲストを含め31人が参加。20代30代の詩人の割合も多く、年齢層が幅広い。那須敦志による斉藤史の戯曲連載、漫画家日野あかねの作品掲載、岡和田晃による「現代北海道文学研究」などゲストも多彩。朗読イベントの開催や歴史市民劇への出演、北海道の詩人の仕事を現代に伝える活動(20号には俊カフェで開催した古川善盛についてのトークイベントを収録)。2021年よりコトバスラムジャパン北海道大会の開催を協力。SNSやYouTubeを活用した告知や海外へも及ぶ交流展開。謹呈・販売用の通常版の他にバーコードの付いたオンデマンド版を平行して発行し、Amazonや楽天ブックスでも販売。2023年よりアフガニスタン国内における詩作禁止令に抵抗する国際連帯の活動を開始。ソマイア・ラミシュの詩・評論を掲載。13号より表紙写真を写真家の谷口雅彦氏が提供。
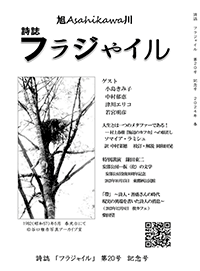
「フラジャイル」
第20号記念号 2024年5月
発行所:フラジャイル党 旭川市春光6条2丁目5番8号
発行・編集人:柴田望
参加者:(文中以外で) 若宮明彦・吉成秀夫・澄川智史・木内ゆか
・うのしのぶ・福士文浩・澤井浩・川嶋侑希・清水俊司
・枝松夏生・吉田圭佑・島つくえ・高細玄一・丁章
・土師一樹・諸橋亜桜・廣石万葉 他
(「フラジャイル」発行・編集人)
俳句同人誌の自由と孤独
俳句同人誌の自由と孤独
五十嵐秀彦
〈アジール 【独 asyl】 民俗学でいうところのいわゆる「避難所」、日本の歴史では網野善彦の「公界」、つまり中世の「かけこみ寺」をイメージしていただければよいでしょう。俳句の世界で同人誌はアジールなのかもしれません。〉
俳誌「ASYL アジール」は2021年暮れにこんな文章で始まる創刊準備号を出し、2022年に創刊号を出しました。以降は季刊としながら労力と気力が不足していて毎号遅刊続きです。同人は、青山酔鳴・安藤由紀・五十嵐秀彦・Fよしと・彼方ひらく・近藤由香子・田島ハル・土井探花・村上海斗の9名(五十音順)による船出。創刊早々に同人の土井探花(千葉県)が2023年度現代俳句新人賞を受賞するという快挙があり、「アジール」の名がいきなり全国で注目されることになったものの、同人誌としてはきわめて弱体のささやかな冊子に過ぎません。
YLかつて「結社=俳壇」であった俳句の世界が、近年になって崩れ始めてきました。そんな時代の風を感じながら、あえてアナログの紙媒体として俳誌を発行したところに多少ゲリラ的な気持ちがあるのです。表現者として孤独と向き合う。これが組織に頼らない今後の俳人の方向性となって欲しい。それにはやはり主宰のいない同人誌がふさわしいはず。さて、どうなることやら。
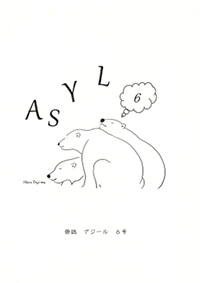
「ASYL アジール」
6号 2023年12月
逢へないと知りたるままに花を訪ひ 青山酔鳴
雪だるま融けて滅びの神ひとつ 安藤由起
鉄砲百合ユイスマンスは生臭し 五十嵐秀彦
ペン先をいつも尖らせ春の雪 Fよしと
凍渡りでいだらぼつちが会ひにくる 彼方ひらく
繭となる逮夜降りつむ雪の音 近藤由香子
百年の春を賜る通知音 田島ハル
白蝶はみんな中古となりますが 土井探花
水温む敬語の混ざる距離感で 村上海斗
(俳誌「アジール」代表)
歌誌「かぎろひ」
歌誌「かぎろひ」
桑原 憂太郎
旭川市に発行所を持つ、短歌結社「かぎろひ」詩社の歌誌である。
「かぎろひ」詩社は、短歌結社であるから、その歌誌は正確には同人誌ではなく、結社誌ということになる。
けれど、結社誌といっても、主宰や編集人による「選歌」と「添削」がない。送稿された短歌作品は、そのまま、すべて雑誌に掲載される。なので、多分に同人誌的な体裁となっている、といっていいだろう。
そんな歌誌「かぎろひ」であるが、2024年は、創刊70周年を迎えた。人間でいえば古稀であり、まさしく「人生七十古来稀なり」の雑誌だ。そんな、息の長い雑誌だから、創刊時のことを知っている人は、もう、だれもいない。発行人も、私で5代目となった。長ければいいというものではないが、よく継続しているものだと思う。
年6回発行で、会費は年額6,000円。この金額は、破格ではないだろうか。月額500円だ。もしかしたら日本で一番会費の安い短歌結社ではないかと思っているけど、違うかしら。安価な理由は、原稿の打ち込みから、割付から、校正から、すべて結社内でやって、印刷製本だけ、ネット通販のオンデマンド制作、という工程をとっているためである。デジタル社会の恩恵による、現代の家内制手工業の確立といったところだ。
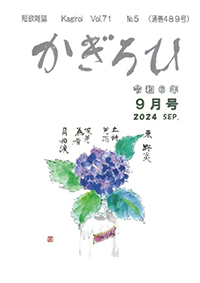
「かぎろひ」
第71号第5号 2024年9月
作品は毎回、30人余りが送稿。だいたいひとり10首くらい。そのほかに、短歌関係の連載や歌評などを載せて、毎号40ページくらい。
表紙の書字、ならびに、壜にささったアジサイの表紙絵は、故石山宗晏氏のもの。石山氏は、3代目の発行人だった人で、書も絵も歌もやる多才な人であった。
掲載作品は、格調高い文語定型から、エッジの効いた口語自由律まで、新かな旧かなまぜこぜ、作風は各人各様、自由闊達。編集人としては、そんな統一感のない、バラバラな感じが、あたかもカラフルなパッチワークを作っているみたいで、毎回の編集はとても楽しい。
(歌誌「かぎろひ」編集発行人)
「川柳さっぽろ」1000号の道
「川柳さっぽろ」1000号の道
佐藤 芳行
「川柳さっぽろ」は2025年8月号で通巻第809号となります。創刊号の発行が昭和33年(1958)2月15日ですから、実に67年6ヶ月の歳月が流れたこととなります。
創刊号はB6判孔版タイプ印刷でした。第11号からはB5判、第71号からは現在のA5判での発行となっています。
巻頭言、温風寒風(さっぽろ論壇)、らいらっく集(役員等自選吟)、あかしや集(同人吟)、ぽぷら集(準同人吟)、幌都集(会員吟)、作品鑑賞、交差点(他誌紹介)、川柳サロン(添削教室)、私の好きな句、課題吟、時事川柳、本社句会報、各地句会報などの50ページから70ページの内容です。
表紙のカットは第130号(昭和44年1月) から清水祐幸画伯、第367号(昭和63年10月)からは斎藤大樹氏、第778号(令和5年1月)からは嶋口幸美さんが担当し現在に至っています。
川柳界にも少子高齢化の波が押し寄せており、新型コロナウイルスの感染予防などの影響もあり、会員数の減少・退会、送料・印刷費などの諸物価の高騰が柳誌発行の障害になっています。
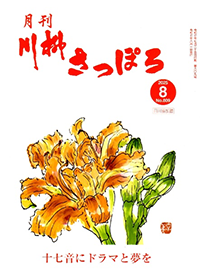
「川柳さっぽろ」
第809号 2025年8月
第1000号への道のりには、山あり谷ありの苦難な道のりも予想されますが、これまでの永きに渡り休むことなく歩み続けてこられた先人の方々の汗と努力の結晶を無駄にすることなく、一冊一冊を積み上げて行かなければと心を新たにしております。
「川柳さっぽろ」が未来永劫光り輝き続け、第1000号へと邁進出来るよう、より良い誌面作りを会員の皆さまと協力し、親しみある「川柳さっぽろ」を目指して行きたいと心も新たにしています。
(「川柳さっぽろ」発行人)
まほうのえんぴつ
魔法の鉛筆を探して
升井 純子
児童文学研究会「まほうのえんぴつ」は、柴村紀代氏の指導のもと、1984年に同人誌「まほうのえんぴつ」を創刊しました。
きびしい指導でしたが、同人は減りませんでした。朱がたくさん入った原稿用紙を家に持ち帰り、次こそは〇をもらいたいと改稿をすることに、少しずつ書く喜びを感じていきました。
多忙なために先生が去られても、同人だけでサークルを運営し、今に至っています。
長く続けていると、会員の入れ替わりもあります。一度遠くの地に行って戻ってきた人もいました。二度と会えないところに旅立ってしまった人もいました。
月に一度の例会では、創作作品や評論、詩などを読み合います。「ここの意味がとりにくい」「もっといい表現はないか」「そもそも構成から見直しては」などと、歯に衣着せぬ意見が飛び交います。くやしい思い、うれしい思い……、それらをどう取捨選択するかは作者に任されます。こうして意見をぶつけ合った作品がのちに商業出版されたり、「約束の町」で、有田美江さんが北海道新聞文学賞を受賞したのは、わたしたちの大きな誇りとなりました。
コロナ禍のときは、数度月例会を閉じましたが、どうしても雑誌発行のために集まらねばならなくなり、一度、札幌駅北口の地下道で例会をもちました。道行く人たちにいぶかしげに見られながらも、長く会っていない家族に再会したときのような、うれし泣きしたいような、そんな感覚を味わいました。
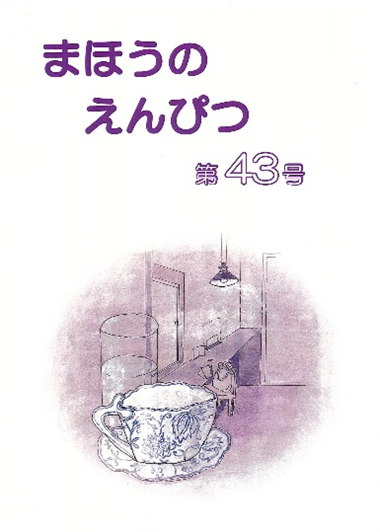
「まほうのえんぴつ」
43号 2024年9月
今は「まほうのえんぴつ」44号の編集の最中です。詩があるでしょうか、書評は何編あるでしょうか、はたまた、絵本は? 自由な誌風のもと、書きたいものを書くわたしたちがそこにいます。
最近よく近所を歩きます。小学生が友だちに手をふっている姿や、お年寄りがひとりゆっくりと歩いている背中を見送ったあと、「どこかに落ちていないか、魔法の鉛筆」などとひとりごちながら、同人に読んでもらう次の主人公像を考えています。
(まほうのえんぴつ代表)
奔流
多喜二を受け継ぐ「奔流」
松木 新
「奔流」は、日本民主主義文学会札幌支部の支部誌で、年一回発行しています。
文学会は、戦後の民主主義文学運動の歴史と伝統を引き継いで、1965年8月に創立、今年で60周年を迎えます。民主的進歩的な文学を求める人なら誰もが参加できる組織で、月刊誌「民主文学」を3,000部発行、全国各地に90の支部が存在、例会を開き支部誌を発行しています。
札幌支部も、月一回例会を開催、「民主文学」掲載作品の合評を中心に、小説の書き方、批評の仕方などを論議しています。月一回発行の「札幌民主文学通信」に、各自が合評作品についての「意見」を発表、支部のHPに「通信」をアップして全国に発信しています。
最新の「奔流」31号はA5版、154ページで、評論3編、読書ノート1編、小説9編、エッセイ2編を掲載しています。これらの作品は、例会で十分な時間をとって合評しています。合評を受けた作者から、さまざまな感想が寄せられています。
「書くことによって今の自分の考えを整理し、次への道を模索してきたように思います」、「合評は、率直な意見交換ができ、楽しく学べる場なので感謝しています」、「会話を入れる大切さ、説明でなくエピソードでなど、書きながら悩んでいた部分に、凄くピッタリの助言を数々いただき嬉しかったです」、「〈ここに質問、疑問が来るであろう〉と、想像していた箇所が、ことごとく、違っていたことには、啞然としました。〈読者に寄り添う心がたりなかったのかなあ〉と思い悩んでいます」。
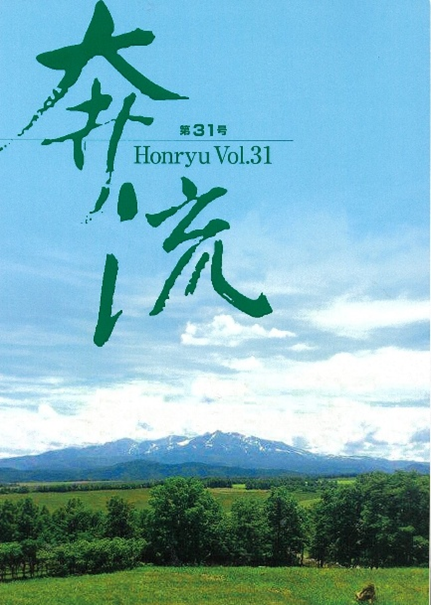
「奔流」
31号 2024年11月
『奔流』の題字は、プロレタリア作家江口渙の揮毫で、札幌支部の誇りでもあります。
札幌支部は、現実の矛盾から目を逸らすことなく、現実に埋没しない批評精神に立ち、いかに生きるかを問い、社会と人間の真実を描くことをめざして、たゆまぬ努力をつづけています。
(民主主義文学会札幌支部長)
葦牙
「葦牙」その源流をたどる
尾村 勝彦
「葦牙」の創刊は昭和12年だが、その前身である「時雨」を改題、継承したものであり、通算すると104年を越えるにいたった。
「時雨」の志向するところは、創刊号の巻頭言のとおり“吾等は誹諧の正道を歩まんとす……吾等は不易の正調を詠はん“であった。
「葦牙」もまたその精神を継承し、“穏健中正、有季定型をつらぬき新鮮かつ風土に密着した作風を目ざす“としている。
「時雨」の創設者、牛島滕六は北海道の風土の特異性に着目し、「道内俳人は北海道の風土に立脚した俳句を作るべし」とし、北方季題の発掘に努めた。そのため、全道くまなく(千島にいたるまで)足跡をのこしている。
こんにち、「葦牙」がモットーとしている“不易の正調、俳句は風土の詩“はここに源を発している。
以来、「葦牙」においては北方季題に対する取り組みに主眼を置いてきた。すなわち、創刊と同時に北方季題欄をもうけ、この五月号でのべ800回に達した。その間、選者は初代高野草雨から現在にいたる14代、発表された作品の数はゆうに十万句を越える。
令和4年には「葦牙」通刊百周年記念として、これら作品のアンソロジー『北方季題選集・朔北の詩』を刊行した。
また、長年にわたって取り組んできた活動の結実として、平成元年に『北方季題選集』を、その補完として平成13年には『北方季題第二集』をそれぞれ発刊し、おおかたの参考に供している。
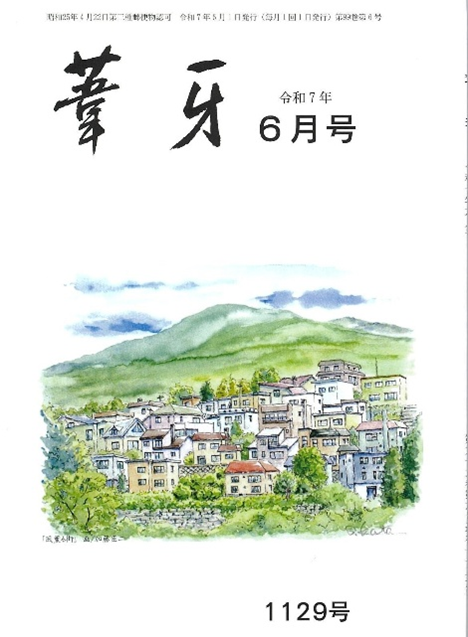
「葦牙」
1129号 2025年6月
創刊以来百年、さきの大戦をはさんで時代は大きく代わった。時代感覚の変化は言うまでもない。伝統を大切にすることは言うまでもないが、つねに新しいものに向かって前進する謙虚な心構えと柔軟な態度が必要であると、自ら深く戒めて来た。
伝統を守りつつ、清新な叙情を目指す、それが目下の姿勢、そして念願である。
(「葦牙」主宰)
札幌文学
1000号発行を目指して
坂本 順子
札幌文学は1925年1月、「旺盛な創作意欲と実行力、自信と熱意のなか全能力を傾けて」創刊されました。酒を飲み交わし侃々諤々の例会は「灰皿が飛ぶことも」。当時の熱気が想像できます。東直巳、髙橋揆一郎、小檜山博、原田康子、木野工氏など著名な方が「札幌文学に草畦を脱いでいった」そうです。
澤田誠一・田中和夫氏は札幌文学の中心でありつつ己れの生涯をかけて北海道の文学運動、特に同人誌活動を牽引してきました。当文学会の誇りです。
創刊以来、常に発行の危機に直面し、1993年には、「柱も屋根も老朽化している家に今更若い人を入れても落ち着くまい。いっそ今の住人たちだけで続けて、その大半が欠けたらその時こそ『札幌文学』を終わらせる」と話し合われ、創刊50年の2000年には、「同人の数は五指をわずかに超えるだけ。しかも80才を筆頭に老齢グループになりつつある。今後、私達の後を引き継いでくれる書き手が出現するまで発行日を定めずにいい作品が集まったときに随時」と、2年おきの発行も度々ありました。
現在、多くの同人誌が廃・終刊し、「存亡の危機」「明日は我が身」との声が聞かれますが札幌の文学も同じです。病気、高齢、死去などなどで同人が減り、物価高騰のなか印刷部数を減らし、年一回の発行で維持しています。書き手の同人をどうやって増やしていくかが悩みどころで、良い知恵がほしいのが実情です。
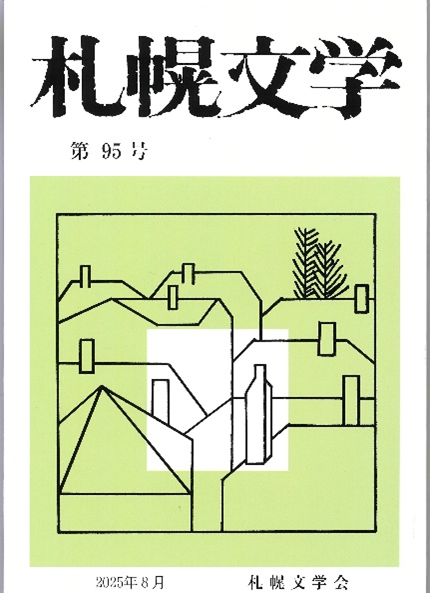
「札幌文学」
95号 2025年8月
同時にいちばん心配なのは、諸先輩が築き上げてきた歴史ある「札幌文芸」にふさわしい内容になっているのかと不安を抱えています。紆余曲折を経ながら今なお継続することが出来ている札幌文学に「良い」作品を書きたいと努力し、厳しい批評もいただきながら、どんなことがあっても100号まで発行しよう(あと5年)と同人の思いは一致しています。
根底には、急逝した田中和夫前代表の『北海道の同人雑誌の灯は消さない』の遺志を受け継ぐ揺るぎない決意があるのです。
(札幌文学会発行人)
北海道アララギ
斎藤茂吉・土屋文明の写実主義を継承
阿知良 光治
本誌「北海道アララギ」は昭和31年、武藤義友氏を中心に函館にて創刊されてから70年目を迎える。現在通巻822号に至った。本誌は斎藤茂吉・土屋文明の短歌雑誌「アララギ」の地方紙として「羊蹄」の後継である。「アララギ」は斎藤茂吉・土屋文明による「写実主義」を基調に歌壇の中心として発展してきたが、平成九熱に終刊を迎えた。その「写実主義」は、「現実に根差し自身の感動を直截に詠う。」のが基本であるが、しかし「写実主義」は必ずしも身の回りの事実を拾い集める事ではない。どんな時にも作者の詩心が働いての現実主義でなければならない。主体的な詩心、また鋭い批判の目も必要になってくるだろう。また、少しでも新しい題材を見出していく努力も必要になって来る。ごく日常的な題材でも作者の感情が生き、把握や手法を工夫することで新しく蘇るのである。
このように日々作歌に努力している我々であるが。残念ながら現在、大きな危機に直面している。それは高齢化による会員の減少である。令和五年からは、今まで毎月発行されて来たが、会員減少による資金難から、隔月発行にせざるを得なくなった。また、本年度も計画したホテルでの「第67回北海道アララギ歌会」は参加者が少なく中止せざるを得なくなったのである。
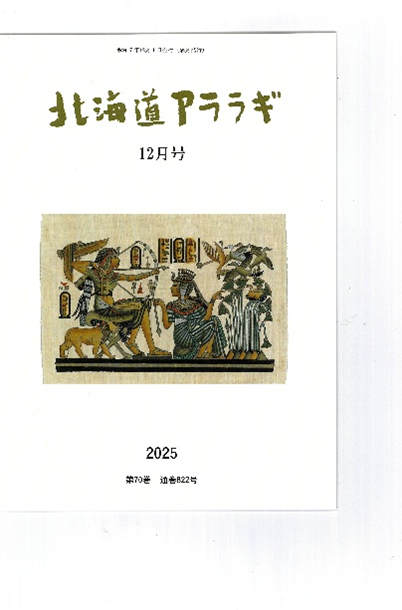
「北海道アララギ」
822号 2025年12月
幸い、苫小牧の有志によると札幌との交流会の要望があり、ミニ短歌会を開催することが出来た。参加者は多くはなかったが、和やかで有意義な会であった。今後はホテルを利用しての歌会は無理ではないかと考えており、こうした各地との交流会の方向で進めていくつもりである。北海道での「アララギ」の灯を消してはならないと考えている毎日である。
(北海道アララギ編集発行人)
小樽詩話会
みんなの『小樽詩話会』
根深 昌博
1963(昭和38)年9月25日午後6時、小樽市内の喫茶店に、4人の世話人の呼びかけに呼応した男女19人の青年が集いました。そして、詩を中心に「文学について自由に話し合える場」として『小樽詩話会』は発足しました。
現在、会員52名(会費・月額1,000円)、購読会員33名(年会費・5,000円)で活動しています。
会報(40~50ページ)は隔月で年6回、偶数月に発行しています。2025年12月で662号。
8年前までは50数年間毎月発行していましたが、いま振り返ると驚嘆すべきことでした。さらに、毎年会報とは別に記念号も発行しています。
伝統的に、発足当初から例会(合評会)に重点を置き、顔の見える関係にこだわっています。単なる投稿誌になることを避け、合評会を最重要視しています。また、同人誌という認識もありません。そのため、散文も掲載可能ですし、寄せられた原稿は、よほどでない限りどんな作品でも必ず掲載します。基本は、詩作や詩を通して「楽しく豊かな人生を」が、変わらぬ会の主旨です。
誇示するわけではありませんが、詩集を上梓された会員の中から、何人もの方が賞(道新文学賞、小熊英雄賞など)を受賞しています。昨年も会員が道新文学賞を受賞しました。
他に幾つかの、小樽詩話会ならではの特長を紹介します。
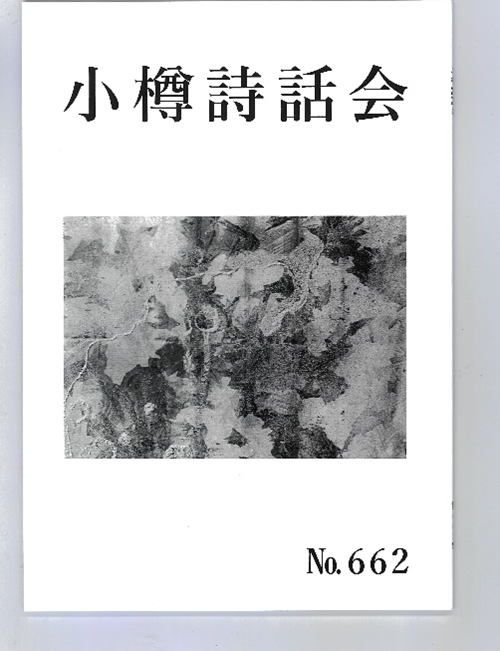
「小樽詩話会」
622号 2025年12月
☆会則がない~自由な発言、柔軟な発想を妨げることのないよ
う、暗黙裡に大人の振る舞い
が求められている。政治や宗教
などイデオロギーを持ち込まないことが不文律になっている。
☆世話人~世話人は主宰者でも会長でもない。文字通り、
会のお世話に徹する潤滑油である。
誰かの「会」になること
を恐れ、ヒエラルキーの排除につとめた発足時の先輩諸氏の
智慧です。
☆月2回の例会~発足以来コロナ禍を除き、毎月5日と20日に
必ず例会を開いている。
今年10月に1,400回を迎える。
結びに~小樽詩話会は、誰かの「会」ではなく、みんなの「小樽詩話会」です。
これからも、この発足のスピリッツは変わりません。
(小樽詩話会 世話人)